訪問看護ステーションで勤務していると、ビジネスパートナーである介護支援専門員(ケアマネジャー)との関わりも多くあります。
ご利用者の状態をはじめ、看護やリハビリ時の様子、ご家族や生活環境への配慮など、ケアマネジャーからいただくご質問も多くありますよね。

その中でも今回は、比較的多いなと感じる質問を取り上げてみました。
この「ケアマネジャーからよくある質問5選」を通して、訪問看護に関わる介護保険や医療保険制度の理解が深まり、訪問看護・リハビリをもっと知っていただける機会になればと思います。
ケアマネジャーからよくある質問5選
1.「難病」=「医療保険」??
ケアマネジャーとの会話や新規相談の中で時折、「難病の方は医療保険でのサービスになりますか??」というご質問をいただくことがあります。
結論、「難病=医療保険」ではないんです。



「難病」と聞くと、「医療保険かな?」とつい思ってしまいますよね。



申請すると発行される指定難病医療費受給者証にも、“医療費”と記載がありますしね〜。
では、難病で医療保険が適応となるのはどのような場合か…??
これは至ってシンプルです。
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当するご利用者が医療保険の適応となります。



逆に言えば、この別表7に該当しないご病気のご利用者は、難病であっても介護保険が適応ということなんです。
2.「訪問看護指示書」は複数必要??



こちらは、1人のご利用者に対して複数の訪問看護ステーションが関わる際に、時折聞かれるご質問ですね。
結論、訪問看護指示書は「1枚」となります。



「ご利用には訪問看護指示書が必須」であることはご存知の方も多いですが、意外と知らないこともありますよね。
- 指示書は1人のご利用者に対し1枚。
- 指示書を発行できる主治医も1カ所のみ。
- 複数の訪問看護ステーションで共有。
- 訪問看護指示書料(書類代)も1枚分。(主治医にとってはデメリット)



「特別」訪問看護指示書については、「一般」訪問看護指示書とセットで発行していただく必要がありますのでご注意を!!
3.通院(外来)リハビリやデイサービスとの併用はできる??



退院後やプラン見直しの際のケアプラン作成にあたり、このご質問を受けることがありますね。
結論、併用は可能です。
ケアプラン上で各サービスの役割を明確にすることが前提であり、さらにはご利用者のニーズに合わせることが重要なポイントですね。
- 訪問看護のリハビリは「訪問看護Ⅰ5」
- 報酬上は訪問看護としての位置付けとなる
4.訪問看護のリハビリは週何回まで可能??
これは同じ訪問看護のリハビリでも、介護保険と医療保険で違いがあるんです。



介護保険を主としてプランを組まれるケアマネジャーからすると、ここはややこしい点ですよね。
介護保険の場合は??
訪問看護のリハビリは、
1週間で「120分」が上限となります。
※看護師の訪問回数は含まない。
つまり、40分を1回とした場合、
週3回のリハビリが上限ということですね。
※60分の場合は週2回。
医療保険の場合は??
通常の医療保険では、
1週間で「週3回」が上限となります。
※看護師の訪問回数を含む。
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)では
1週間で「週4回以上」の医療訪問が可能です。



その他、特別指示期間中も医療保険に該当します。
情報整理が大変ですよね(汗)
5.令和3年介護保険制度の改訂内容(主にリハビリ関連)



今回の改訂では、その他の介護保険サービスの中でも、訪問看護におけるリハビリに対する減算はなかなか厳しいものでしたね。
この件に関して、ケアマネジャーからの問い合わせが多かったのは以下の2つでした。
①基本報酬(単位数)の減算の内容は??
・訪看Ⅰ5(20分)の場合
297単位 → 293単位(4単位減)
・予訪看Ⅰ5(20分)の場合
287単位 → 283単位(4単位減)



40分のリハビリで8単位減ですね!
②要支援ご利用者のリハビリ(予訪看Ⅰ5)は、12ヶ月超えるとどうなるの??
上記の減算後の283単位(4単位減)から、
さらに5単位減となるんです。



予防訪看の場合、改訂による減算は合計18単位…(泣)
- 和3年4月以降の利用開始月からの12ヶ月
- カウントは「利用のあった月の合計」
つまり、利用開始月以降にサービス利用のない月があった場合(体調不良など)、その月はカウントしません。
とはいえ、合計12ヶ月ということには変わりはなく、その他の制約もいくつかあるので注意が必要ですね〜
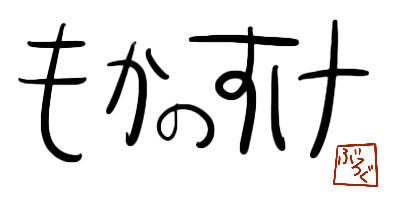
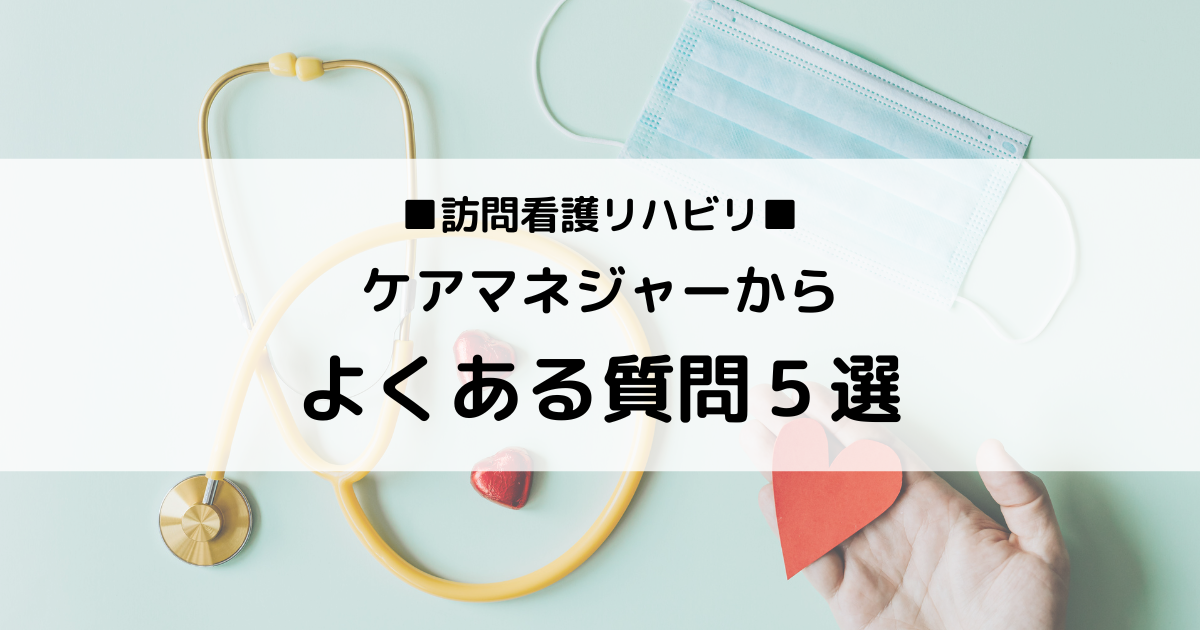

コメント