訪問看護ステーションからの訪問を依頼する(または提供する)にあたり、
介護保険内での訪問になるのか、または医療保険内での訪問になるのか、
分からずに不安になったことはありませんか??
その代表とも言えるものが、この「厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)」ですね。
今回はこの「別表7」の内容や注意点について、私の経験も踏まえて解説していきます。
この記事をみることで、皆さんの疑問や悩みが解決し、かつ「知ってよかった」「読んでよかった」と感じていただけると思います。ぜひ最後まで覧ください。
厚生労働大臣が定める疾病(別表7)は 医療保険?介護保険?
1、介護保険ではなく、医療保険。
早速結論ですが、「医療保険」が適応となります。
65歳以上の方(第1号被保険者)や、40歳以上の方(第2号被保険者)は、
本来であれば介護保険が優先されますが、
この別表7の疾病に該当すると医療保険の適用となると覚えておいてください。
では、そもそもこの「別表7」とは何なのか、なぜ医療保険の適応になるのか??
次にその解説をしていきます。
2、「別表7」とは何?? なぜ医療保険が適応になるのか??
厚生労働大臣の定める疾病等(別表7)に該当するご利用者は、重症度が高く、医療ニーズが高いご利用者です。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症(※)
- 重症筋無力症(※)
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症(※)
- 脊髄小脳変性症(※)
- ハンチントン病(※)
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(※)
- 進行性核上性麻痺,
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病
- (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(※)
- 線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症
- シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病(※)
- 亜急性硬化性全脳炎(※)
- ライソーゾーム病(※)
- 副腎白質ジストロフィー(※)
- 脊髄性筋委縮症(※)
- 球脊髄性筋委縮症(※)
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(※)
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
(※)下線は「指定難病」
上の表にある20項目が、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)となります。
中でも、下線の疾病は「指定難病」といわれるものです。
医療保険の適応になる理由としては、この「指定難病」をもとにすると考えやすいのではないでしょうか??
- 発病の機構が明らかでない
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病
- 長期の療養を必要とするもの
- 難病の中でも患者数が一定数を超えず、
- しかも客観的な診断基準がそろっていること
- さらに重症度分類で一定程度以上であること
とされており、現在国内では300を超える疾病が指定難病に登録されています。
中でもこの別表7に挙げられる疾病等は特に重症度が高く、医療ニーズが高いとされています。
そのために「医療保険」を優先したサービスの提供が可能(必要)となっているわけですね。
私が関わってきたご利用者の中にも20項目に該当する方は多くおられましたが、やはり介護保険内では足りない程のサービスが必要でしたし、医療費助成に助けられたと言われるご家族様もいらっしゃいましたね。
3、よく見て。訪問看護指示書の「傷病名」。
私の経験上、細心の注意が必要な点は訪問看護指示書の「傷病名」です。
傷病名は主治医により診断されたその方の疾患ですが、一体何に注意する必要があるのか…??
それは、傷病名が「別表7と同一」であることを必ず確認する、ということです。
この確認を怠ると、本来介護保険が優先されるにもかかわらず、誤って医療保険でサービス提供をしてしまう可能性があります。
2つ例を挙げるとすれば、「頸髄損傷」と「パーキンソン病」です。
まず「頸髄損傷」ですが、似たような傷病名に「頚椎損傷」がありますね。
お分かりかと思いますが、この「頚椎損傷」は医療保険でサービス提供ができる傷病名ではなく、介護保険が優先される傷病名となります。
これを聞くと、少しドキッとしませんか??
意外と見落としていたり、「頸髄損傷」と思い込んでいる場合があるので、細心の注意が必要です。
次に「パーキンソン病」です。
もうお分かりかと思いますが、「パーキンソン病」だけでは、医療保険でのサービス提供はできません。
別表7をよく見てみましょう。
「ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る」
そうなんです。医療保険が適応になるのは、「ホーエン・ヤールの重症度分類」と「生活機能障害度」の記載が併せて必要であり、かつ重症度(障害度)が条件を満たすものに限る。
その場合に初めて、医療保険が適応となります。
そうしなければ、介護保険と医療保険での境界線があやふやになり、後々誤った請求であったことが発覚する場合などもあります。
あくまでもこれば一例(二例)ですが、私達訪問看護に従事するものであれば、その点の知識はしっかりと把握しなければなりませんね。
まとめ
今回は、「厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)についてシンプルにまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか??
頭では解っているつもりでも、意外と混乱しやすい内容ではないでしょうか。私自身、経験が浅いときには何度も確認したものです。(間違ってはいけないので、日々ビビってました。笑)
この内容は、ケアマネジャーからも質問や相談をお受けすることがあります。(介護保険を専門に取り扱う方々ですので、当然ではありますが。)
そんな時に、少しでも不安や悩みを解決できるよう、ドシッと構えておきたいですよね。
医療ニーズが高く、かつ介護保険サービスを必要とする方も多くいらっしゃいますので、私達訪問看護に従事するものが、少しでもお役に立てるように今後も努めていきたいものです。
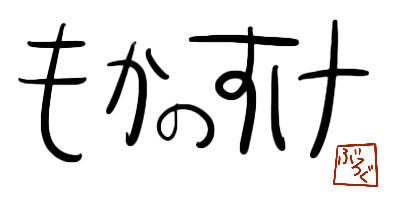

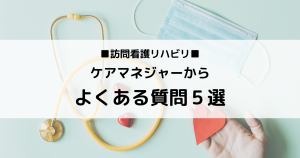
コメント